今回のブログでは、まず、オーストラリアの公共放送ABCのラジオ番組Big Ideasで放送された、イギリス保守派の論客であるダニエル・ハナン[Daniel Hannan]の講演の内容をかいつまんで紹介します。これは、オーストラリアのリバタリアニズムのシンクタンクである「独立研究センターCentre for Independent Studies」でダニエル・ハナンが行った「アイデンティティー・ポリティクスがいかに啓蒙思想を逆戻りさせているか」という題の講演です。
【アイデンティティ・ポリティクス】
差別用語をなくす必要があるのは多くの人が認めることでしょう。ただ、political correctness [政治的妥当性]を追求しすぎると、行き過ぎた言葉狩りが行われるようになります。ダニエル・ハナンは、今の時代は 〝アイデンティティ・ポリティクス〟の分野で、競って自らの美徳を誇示することが行われていると言います。百年前の小説の言葉遣いが現在の尺度から見て不適切であると指摘するだけでは十分でなく、今まで誰も何とも思わなかったような事柄を取り上げて、自分がいかに敏感であり、それがいかにひどいことであるかを指摘するのが徳であると思われているふしがあるというのです。たとえば、ハリー・ポッターの物語のなかにLGBTコミュニティの人々の模範となるような登場人物がいないのがとんでもないことだと主張して、自分が一般の人々より優れていることを示そうとする態度です。これが進むにつれて、社会のいろいろな点についてかなり攻撃的な憤慨を示す人々が出てきます。この事態は、政治的妥当性が〝荒れ狂った〟のだと言うだけでは不充分で、もっと重大な事柄が進行していることに気づく必要があるとハナンは主張します。
次のような状況が欧米にはあります。例えば、白人でイギリス人であるハナン自身が「イスラム教は同性愛を受け入れるのが困難だ」というような発言をすると、彼がムスリムであるかどうか、同性愛者であるかどうかによって、そのような発言をする権利があるかどうか判断される傾向があるのです。つまり、ある人の発言が、その内容自体に真実があるかどうかでなく、発言者のアイデンティティや皮膚の色で規定されるわけです。これはすなわち近代の啓蒙主義および西洋文化が基盤にしている考え方から後退することにほかなりません。私たちの意見は生まれた時点で決定された私たちのアイデンティティによって規定され、発言内容自体に評価すべきことがあるかどうかはまったく関係ないという考えは、近代以前の身分制度に逆戻りするものだというわけです。
およそ一万年の間、すべての人間関係は生まれや身分・伝統に取り仕切られていました。近代の啓蒙思想の真髄であり、現代のように豊かで快適な生活が営める理にかなった社会の根幹にあるのは、私たちはみな個人として自律しており、さまざまな人々と自由に取り決めすることができる、という考え方です。許される行動や発言があらかじめ、自分で選んだのではない外的な特徴によって規定されているという考え方はそれと真っ向から対立します。
政治的妥当性に似た、cultural appropriation[文化的不正流用]という概念も欧米で広まっています。文化的に優勢な集団に属する人が不利な条件にあるマイノリティーの文化を勝手に使用・流用するべきではないということですが、この「文化的不正流用」(cultural appropriation)という語は2019年2月現在日本語版ウィキペディアにまだ掲載されていません。文化的不正流用が行われると、流用された事柄はもともとの文化的な意味を失っており、文化を勝手に使われたマイノリティー集団の知的財産が侵害された言ってもよく、単にエキゾチックであるということで文化が流用されるのは植民地主義にほかならないという見方です。国際的に有名な料理人であるジェイミー・オリバーが昨年8月に発表した「ジャマイカン・ジャーク・ライス」が、イギリス野党の平等問題担当の国会議員から、そんなものは本当のジャマイカのジャークではないという指摘があり、問題になりました。ジャマイカ人以外の人間がジャマイカ料理に触発された料理を創ってはいけないということになりますが、ハナンに言わせれば、料理というのは他の文化とのフュージョンが行われるのが当たり前で、オリバーがジャマイカ人ではないからこんなものを作ってはいけないという理屈自体が問題です。
同性愛者ではないジャック・ホワイトホールというイギリスの俳優がディズニーの映画作品でゲイの登場人物の役割を引き受けたことが問題になったそうですが、役者というのはそもそも別人になりきるのが仕事なはずです。このような〝問題〟を鬼の首を取ったように指摘する人がいるわけですが、そもそも、自分の外観・容姿に合った役割だけを演ずるべきなのか、そうではないのか、の二者択一であるはずです。両者を同時に要求することはできません。黒人は黒人の役割しか演じることができないのか、黒人以外の役割を演じてもよいのか、それが決まれば、白人が黒人の役割を演じてもよいのかいけないのかが決定されるはずです。
アメリカの進歩的週刊誌「The Nation」が、ホームレスの黒人女性の視点からアメリカ黒人の言葉遣いで非常に繊細に書かれた詩を掲載したところ、作者が黒人でも女性でもなかったことが判明して、問題になりました。何が何でも憤慨するつもりなら、憤慨すべきことは何にでも見つかります。そのような立場の人々の発言に矛盾があると指摘したところで、受け取る側の感情によってすべてが規定される現在の社会的雰囲気のなかでは、太刀打ちできません。「被害者」の感情が事実よりも優先されるのです。
その点で、affirmative actionと呼ばれるアメリカのマイノリティー優遇措置によって大学入学枠に人種割り当てを設定するのも問題がある、とハナンは主張します。第二次世界大戦が起きる前にヨーロッパ各地の全体主義政府がとった政策がそれにほかならないからです。これらの政府が主張したのは、過少な待遇を受けているのは非ユダヤ系の一般国民で、ユダヤ系の国民は優遇され過ぎているということでした。国民全体のユダヤ系と非ユダヤ系の人口の割合から見ると、大学でユダヤ系の人口が占める割合がずっと高くなっているので、非ユダヤ系の国民がマイノリティーだというわけです。ハナンは、このような形で平等の原則を曲げるのは問題だと主張します。個人の資質・能力によって人を判断するのか、容姿などそれ以外の属性によって判断するのか。個人を尊重するということは、集団的アイデンティティーを拒否するということです。国家がある民族集団をそれだけが理由で処罰するのが問題であるなら、集団的な優遇措置も問題なはずだというわけです。
最近突如として生まれたのが、物事を内面化・主観化してすべてを自分がどう感じるかという問題にする傾向です。自分の権利が侵害された場合、多くの人がその権利を再びを主張する代わりに、自分は精神的な苦痛を感じると主張することを選択するようになりました。2015年より前には、本人に全く自覚のないまま差別ととられるような言動を起こした場合のmicroaggression[微小侵害]という言葉や先に述べたcultural appropriation[文化的不正流用]、放送などで次の報道にトラウマなどを引き起こす可能性のある内容・映像が含まれていることを警告するtrigger warning[事前警告]、社会的排除を経験している人たちが安心して集まることのできるsafe space、などという言葉は使われていませんでした。若い人たちの通う大学内でこれらの言葉が使われているのですが、この突然の傷つきやすさは何なのでしょう。オックスフォード大学の法学部では、暴力的な事件についての事例を読むときに事前警告が学生に与えられていると言います。
『The Coddling of the American Mind[アメリカ人の心を甘やかす]』という本を書いたジョナサン・ハイトという心理学者は90年代に起こった子育ての変化が傷つきやすい世代をつくっていると言っているそうです。常に大人に見守られているのでなく、子供たちだけで〝予定外・管理ぬき〟の時間を過ごし、少しぐらいけがをしても気にしないで遊べる、あるいは対処できるような子供に育てる必要があるというわけです。‶被害者〟が苦痛を被ったすべての行為が「いじめ」と判断され、大人が何にでも介入するような状況で育った子供たちが大学に進学すると、そんなことになるのではないか、とハナンは問題提起します。誰かが七面鳥のハムが入ったサンドイッチを食べているのを見るだけで〝苦痛を感じる〟という人間が出てくるのではないか、と。厳しい意見や自分が不快に思う人物が存在すること自体は悪いことではないはずです。現在のアイデンティティ・ポリティクスは、実際に起こったことを基盤にする経験主義ではなく、個人の内面の主観的な感情を優先しているようで、それが問題なのです。
近代にヨーロッパが非常な発展を遂げたのは経験主義に基づく科学的な思考を基盤にしたからです。「おれの部族は良い、お前の部族は悪い」という主観に基づく反応の仕方から、「自分たちはすべてのことを知っているわけではない。好きになれないような他人でも、何か役立つことを知っているかもしれない。その意見を聞いて、そこに何らかの真実があるかどうかを客観的に判断するのが得策である」という考え方が、多様性や多元主義に基づき、個々の人々を引き上げる、現代社会をつくったのです。
こんなところがこの放送でダニエル・ハナンが語った内容です。
【個人で判断する】
ハナンは保守派の論客ですが、自分は進歩派であり、彼は保守派だからその意見には耳を貸さないという人がいたら、それこそ経験主義・科学的思考に反することでしょう。日本では、アイデンティティ・ポリティクスや文化的不正流用、あるいは大坂なおみのCMで知られるようになったwhitewash[白塗り]という概念や意識はまだ馴染みが薄いようですが、政府・自民党や安倍首相の国会での答弁や統計不正の問題を見ると、事実に基づく経験主義・科学的思考に対する信義・コミットメントが欠如しているように思えます。2009年から2012年の民主党政権でうまくいかなかったから、やっぱり自民党というブランドでなきゃだめだ、という考え方も、個々の政策でなく〝看板〟を重んじています。忖度とか、上からの意向にしたがって行動するのも、やはりある意味で自分の判断を停止するわけですから、問題です。つまるところ、(集団の福利より個人の利益を重視するという意味ではなく)個人で判断し、責任を持つという意味での「個人主義」が民主主義社会には必要なわけです。
こう考えると、日本の政治の問題点は政治制度の問題というより、人々の個人意識の成熟度や道徳心の問題にあるのではないでしょうか。改革すべき「政治改革」の分野もあるでしょうが、実は文化の問題が大きいのであって、それに対する解決策はやはり子供の教育や人々に対する啓蒙活動でしょう。
朝日新聞の市川速水編集委員が2019年1月27日に「興奮しない日韓関係」という論考を朝日新聞のWEBRONZAに発表しました。その中で市川氏は「韓国は、価値観が変わることに躊躇しない。激しい民主化闘争を経て、平成のスタートごろから軍事独裁を放棄して民主政権へとかじを切った。… 大統領選では熱狂的な支持を集めても、当選するとあっという間に風向きが変わって支持率が落ちる。有権者は後悔し、週末ごとに退陣デモが繰り返される構図は定着している。… その間、国会議員の女性比率は1990年で日韓とも、約2%と低い水準で肩を並べていたが、伝統的に男尊女卑が激しかった韓国では、国会議員選で比例代表のクオータ(割り当て)制を導入するなど女性の政界進出を後押しし、17%まで上げてきた(日本の衆議院は9%)。司法制度の可視化、性犯罪対策など法制化を次々と進め、「MeToo運動」も激しく広がり、政財界を震撼させている。労働・福祉政策の向上を訴える市民デモは日常化している。」と書いています。「それに比べて日本は、韓国とは反対の方向に進んできた。肯定的な言い方をすれば〝ぶれない〟〝一貫している〟〝落ち着いている〟とも表現できる。… 官庁による不適正な調査が分かっても、首相の家族や友人が国の政策判断に関与していることが分かっても、大臣の辞任や政権交代に発展しない。… 歴史の清算についても同様だ。戦争被害や戦争犯罪について、原爆投下の真相糾明・被害回復も、戦争犯罪人の裁きも、日本自らの手ではしてこなかった。日韓請求権協定や日中、日ソなどとの国交正常化についても、条約の本格的な見直しを自国世論に訴え、それをバックに相手国に迫ることはなかった。」と続けます。
(女性議員のクオータが平等の原則に反するのかどうかは、ここでは私の判断を差し控えますが)こう見てみると、良かれ悪しかれ、日本人は自分で判断して行動を起こすという資質に欠けているように思います。
【慰安婦問題】
先日、韓国の国会議長が「天皇が元慰安婦に直接謝罪すれば慰安婦問題は解決する」という考えを示したと報道されました。朝日新聞は韓国の国会報道官が「天皇が…元慰安婦の手を握って謝罪すれば、心のしこりが解けるのではないかというのが…趣旨だった」と説明したと報じています。
これは慰安婦問題が日韓間の政治問題、あるいは慰謝料の問題という、政策やお金の問題だけでなく、実は「心の癒し」、すなわち〝精神文化〟の領域に関わっていることを示すのではないでしょうか。現代社会では市民が「精神文化」「政治・法制」「経済活動」という三つの領域を通じて三重に社会に関わっています。どんな社会問題をとっても、これら三層のすべてをとらえないと全貌が見えないということです。
アイデンティティ・ポリティクスの話につながりますが、国の政策がゆえに不公正に苦痛を強制させられた場合に、法的な立場が是正され、加害者が罰せられ、しかるべき慰謝料を受け取ったとしても、それだけでは心の痛みは癒されないものです。慰安婦問題で言えば、人生の大切な時期を台無しにされただけでなく、その痛みは一生背負い続けてきたはずです。社会的な立場が修復され、経済的に恵まれた生活をするようになっても、まだ何か足りないのです。
オーストラリアでは、カトリック教会など宗教的および非宗教的法人が運営する全寮制の孤児院や学校で1950年代から2000年にいたるまで長期間にわたって児童生徒に対する性的虐待が犯されていました。それが明るみに出てからも、カトリック教会当局などは組織としての責任を認めず、問題が解決されないままでした。そこで、2013年から17年までオーストラリア国会に特別調査委員会[Royal Commission]が開設され、虐待を生き延びた人たち(〝犠牲者victim〟というより〝survivor〟という言葉が好まれます)が多数証言台に立ちました。どのサバイバーも、加害者を罰するだけでなく、それぞれの組織の長に謝罪してもらいたいということを言っていました。カトリックの組織であるなら、ローマ法王が虐待の事実を認め、謝罪するということです。(バチカンではちょうど先週カトリック教会の190人の司教らが集まって教会内での性的虐待について話し合う会議が開かれたところです。)この点で、韓国の元慰安婦が日本の天皇に謝罪してもらえれば心のしこりが解けるのではないか、というのは真実なのではないでしょうか。
さらに、日本の総理大臣でなく、天皇が謝罪するというのが重要なのだと思います。なぜなら、総理大臣は日本の政治制度を代表するのに対し、天皇は日本人の文化を象徴するからです。政治家ではなく、日本人の精神を代表する誰かに謝罪してもらいたいということでしょう。この点で、国家に組み込まれた天皇制ではなく、文化組織として自由にかつ創造性をもって活動する天皇制の可能性について以前のブログで述べました。
何となくすっきりしない「アイデンティティ・ポリティクス」や「文化的不正流用」という問題も、何が政治なのか、何が文化なのか、何が経済なのかを区別し、それぞれ「平等」「自由」「友愛・互恵」という異なる原理を用いて対処するようにすれば、もっとしっくりする解決法が見えてくるのではないかと思います。
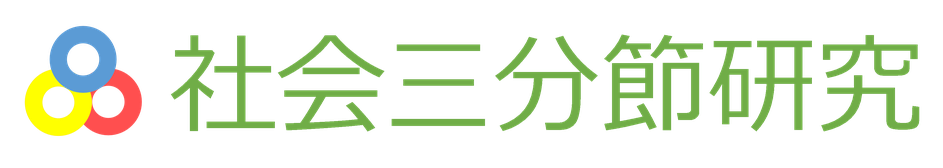
コメントをお書きください